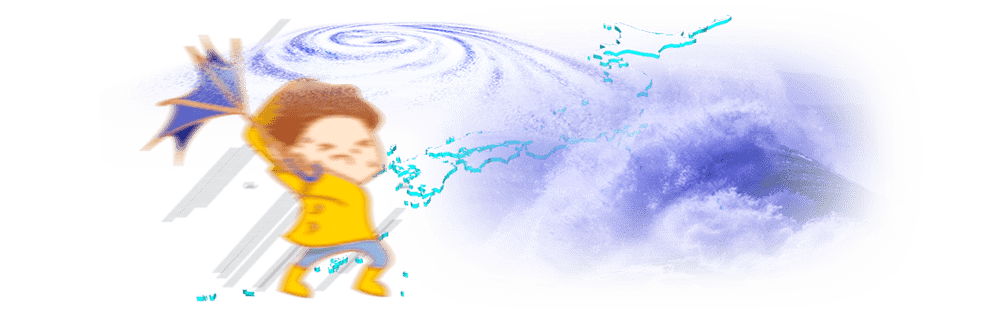「 気象庁長官の許可を得ない天気予報の記事コンテンツ( 情報の中身 )の公開は違法行為ではないのか? 」
過去に別ブログの「 瓦版茨城 」で以下の天気予報の記事を書いた時に、とある内容のご指摘を読者様よりコメント欄に頂いた。↓
気象庁長官の許可を得ているのでしょうか?
天気予報の掲示は違法行為になりますよ。
許可を得ているのでしたら、逆に許可の取り方をお教えいただきたいです。
気象庁の長官から許可を得る「 予報業務許可事業者 」とは、台風を含む予報業務を気象業務法第17条第1項に倣( なら )って行うことが出来る事業者を指す↓。
当時は正直あせったが、不肖この私めの様な気象予報士の資格もない者がブログに台風情報の記事を書いて公開する事は違法行為にあたるのか?
そもそも予報業務許可事業者とは?
気象庁長官の許可を受けて、気象、地震などの地象、津波、高潮、波浪又は
洪水の予報の業務を行う事業者である( 気象業務法第17条第1項 )。日本で俗に民間気象会社と呼ばれているものの多くは、この予報業務許可事業者である。
許可を受けずに予報業務を行った者は、50万円以下の罰金に処せられる( 同法第46条 )。
では、なぜ気象庁は予報業務許可事業者の制度を設けているのか。
予報業務は国民生活や企業活動等と深く関連しており、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表されると、その予報に基いて行動した者に混乱や被害を与えるなど、社会の安寧を損なう恐れがあります。
このため、気象業務法第17条の規定により気象庁以外の者が予報業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならないこととし、予報業務を許可制としています。
つまり、予報業務許可事業者の資格を持たない者が勝手に天気予報などの気象情報を発表すると、社会の混乱を巻き起こす恐れがあるからだ。
では、気象予報である台風情報をブログ記事にして公開するのは違法行為になるのか?
台風情報のブログ記事は違法行為なのか?
では、当「 台風の進路予想と最新情報 」ブログの様な記事コンテンツ( 情報の中身 )は違法行為になるのか?
気象庁以外の事業者が天気や波浪等の予報の業務を行おうとする場合は、気象業務法第17条の規定により、気象庁長官の許可を受けなければなりません。
これは予報業務が国民生活や企業活動等と深く関連しており、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表され、混乱をもたらすことを防ぐ必要があるため、予報業務を許可制としているものです。
許可を受けるには、予報業務を適確に行うための予報資料等の収集及び解析に関する施設や要員を置く等、気象業務法第18条で定められている許可の基準を満たしていることが必要です。
気象庁の公式HPでは、「 天気や波浪などの予報業務を行う場合は気象庁長官の許可が必要 」だとしている。
もちろん「 私めは事業者でなく個人だからカンケーない 」などと、一休さんのような「 とんち 」を言うつもりはない。
だが上記の事例は自分自身が「 天気予報を1次情報として公表する場合 」の話しである。
気象業務法に基づく予報業務の許可が必要なのは、営利・非営利を問わず、業務として予報を行う、すなわち、自ら行った予想を、日常的・継続的に他者に提供( 発表 )する場合である。
家族旅行、工場の生産管理、交通機関の運行管理など、一回限り、または定期的とみられない程度の頻度でしか発表を行わない、あるいは予想の結果を自己責任の範囲内でしか用いない場合は、許可は必要としない。
また、他者の発表した予報をそのまま伝達する場合はもちろん、これに解説を付したり他の地理情報と組み合わせたりした二次コンテンツを発表する業務も、許可を必要としない。
上記引用の中の「 他者の発表した 」の「 他者 」は、むろん公的機関である必要があるが、「 2次コンテンツ 」としての利用であれば、予報業務許可事業者の資格は必要ない。
当「 台風の進路予想と最新情報 」ブログが引用する1次情報の気象機関は、運営者情報の欄で詳しく解説しているので、そちらで!
前章のWikipedia情報は引用部分の記載に対する出典がないので、ちょっと気にはなっていた。 ではアメリカ( 米 )軍JTWCや、ヨーロッパ中期予報センターECMWFおよび、チェコ共和国のWindyなどの海外の気象機関が発表している台風の進路予想図を日本国内で紹介することに関して気象庁の公式見解は、どうなのか? 外国の天気予報を国内で行う場合にも、予報業務許可が必要でしょうか。 予報業務許可制度を定めている気象業務法は国内法ですので、外国の天気予報を行う場合には適用されません。 つまり、気象庁の公式ホームページでは、「 海外の天気予報に関しては、国内法である気象業務法には適用されない 」という見解を定めている。 しかしながら、当「 台風の進路予想と最新情報! 」ブログでは、もちろん日本の気象庁が発表している台風予報を紹介しつつも、「 海外の気象局が予報している日本周辺の台風の進路予想図 」なども掲載しているのだ。 となると、「 外国の天気予報を国内で行う 」こととは、ちょっと意味合いがズレてくる。 では、海外の気象機関が発表している日本の台風情報を日本国内で公開するのは法律違反になるのだろうか? 気象庁の担当者 そのため、公開された結果を紹介するだけなら法律違反にはならないと考えている。 ただし、社会を混乱させないという法律の趣旨をご理解いただき、扱いについては配慮してほしい 」 上の引用部分を要約すると、「 海外の気象機関が発表している日本の天気予報をインターネット上で公表しても法律の対象にはならないので、公開された結果を紹介するだけなら法律違反にはならない 」ということになる。 ただし、海外の気象当局が発表している天気予報などの「 1次情報 」を紹介することが前提条件なので、自分勝手な思いつきでの公開は違法行為となる。海外の気象予報を日本国内で公表する場合
海外の台風情報の紹介に気象庁の担当者は
「『 気象業務法 』は国内法なので、海外の気象当局などが日本の天気を予報して、インターネット上で公開しても、法律の対象にはならない。台風の情報発信に予報業務許可は必要か?
さらに不肖この私めが運営しているYouTubeチャンネル「 台風速報 」の動画でも、視聴者様からコメント欄で次のご指摘をいただいた。
“6月6日時点では気象庁は予測を出していないのに台風情報を出して良いんですか?
確か気象業務法でダメだったような”
しかしながら結論は、「 海外の気象局が発表している1次情報である台風予報を『 紹介 』するだけなら法律違反には当たらない 」のである。
気象庁の発表した予報や他の許可事業者が発表した予報を解説するだけであれば、予報業務許可は必要ありません。
ただし、「 社会を混乱させないという法律の趣旨を理解して情報の扱いについては配慮すべし 」ということになる。
以上の点を踏まえつつ、当「 台風の進路予想と最新情報! 」ブログでは社会を混乱させないよう配慮しながら、今後も台風に関する情報発信を続けてまいる所存だ。